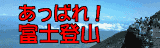S.Kさん
1956年の焼印
古い時代の富士山の焼印の写真を送っていただきました。実に貴重なものです。1956年に登山された方は船津口から登り、吉田大沢の砂走りで下山、吉田口の馬返しに到達したと思われます。
(S.Kさんのメール)
自宅にある金剛杖の焼印がかなり古い時代のものなので、画像を添付してみます。船津口など今ではなくなってしまった登山口のものです。この杖を使って富士登山をした際に、山小屋の方に焼印をお願いすると年配の方から「お宝の金剛杖」だと感心されました。

1956年(昭和31年)。丙申(ひのえさる)
富士山は庚申(かのえさる)の年に誕生したという伝説があり、申年に富士登山をすると縁起が良いとされています。
船津口

船津口は現在の富士スバルラインの近くにあった登山道で、三合目までは登山バスが走っていました。その便利さから、1964年に富士スバルラインが開通するまで賑わいました。三合目から五合目までは急坂に強い特殊車両が通行可能でしたが、四合目の焼印があるので歩いて登られたようです。船津口五合目は現在のスバルライン五合目です。
五合目から胸突き八丁

天地之界は下山時の可能性もあります。雲上界六合目に重なった「本七合目」は1981年の押印でしょう。
下山(砂走り)

1956年当時は八合目から吉田大沢が下山道として使われていました。「サンドスキー」という表現が面白いです。歩かなくても、ずるずると滑っていけるほど柔らかな砂地だったのかもしれません。六合目(標高2500m)に至ります。
富士嶽神社

吉田口馬返し(標高1450m)にあった神社。左の写真はサル。右の写真は「不浄除」。居座っているのはクマに見えます。
桂屋

吉田口馬返し(標高1450m)にあった山小屋「桂屋」の焼印。
1981年